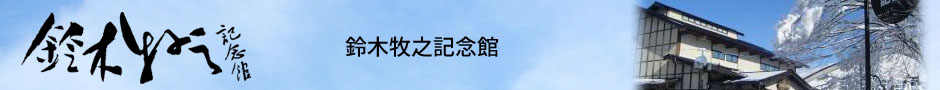
鈴木 牧之(すずき ぼくし)
 『北越雪譜』の著者、鈴木牧之は明和7年(1770)塩沢に
『北越雪譜』の著者、鈴木牧之は明和7年(1770)塩沢に
生れました。幼名:弥太郎、元服後:儀三治
牧之の家は、代々縮の仲買商を家業とし、父の影響を
受け幼い頃から学問や文芸の道に励みました。
父親は俳諧に親しみ、俳号を「牧水」と名のっていました。
息子も、それを習い「牧之(ぼくし)」と俳号を決めたのでした。
牧之の交友は広く、作家では山東京伝や弟の山東京山、
十返舎一九、滝沢馬琴など、その他、画家や書家、俳人、
役者など200人余りにのぼっています。
学問や文芸にたけ几帳面であった牧之が遺した資料から、
当時の文人や画家などの様子をうかがい知ることができ
ます。
牧之の座像は、牧之が描いた「父母の図」の父 恒右衛門と
牧之の子孫青木源左衛門の写真からモンタージュされ、
昭和8年、浦佐(現南魚沼市浦佐)の彫刻家 井口喜夫氏によって制作されました。

